理念
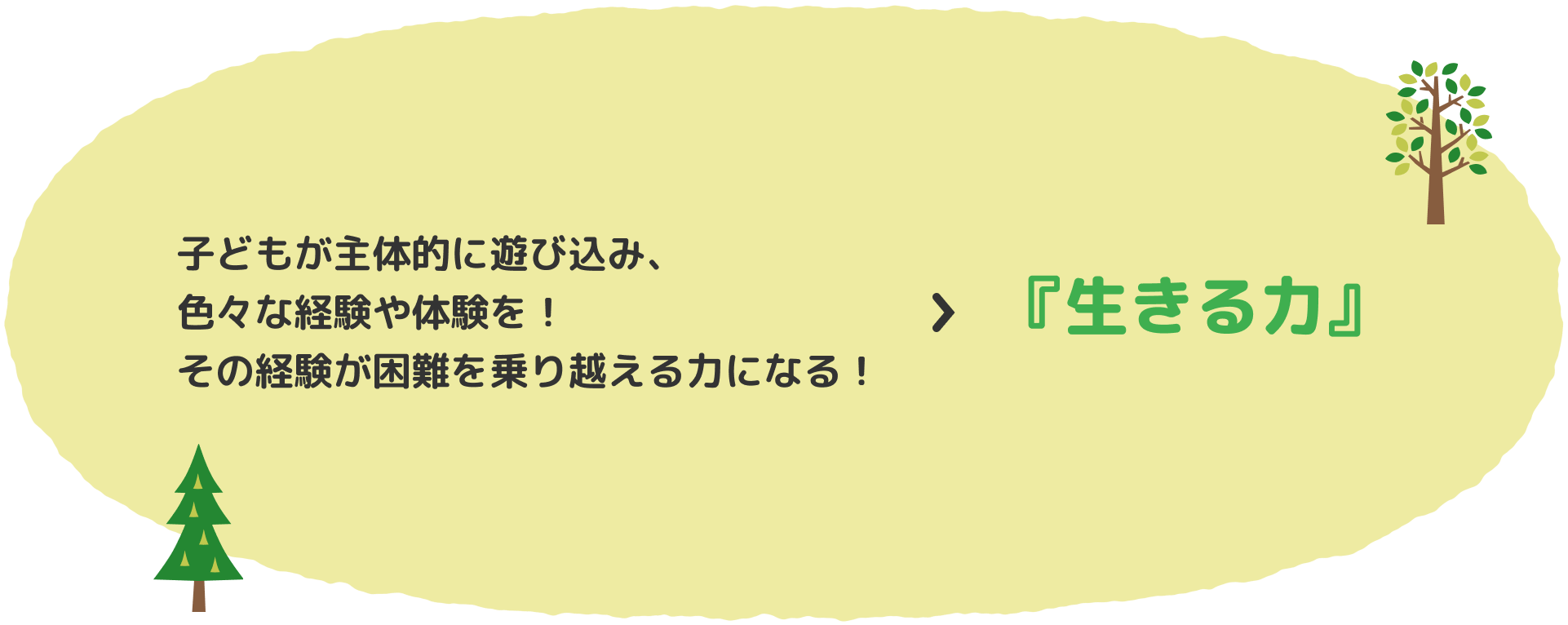
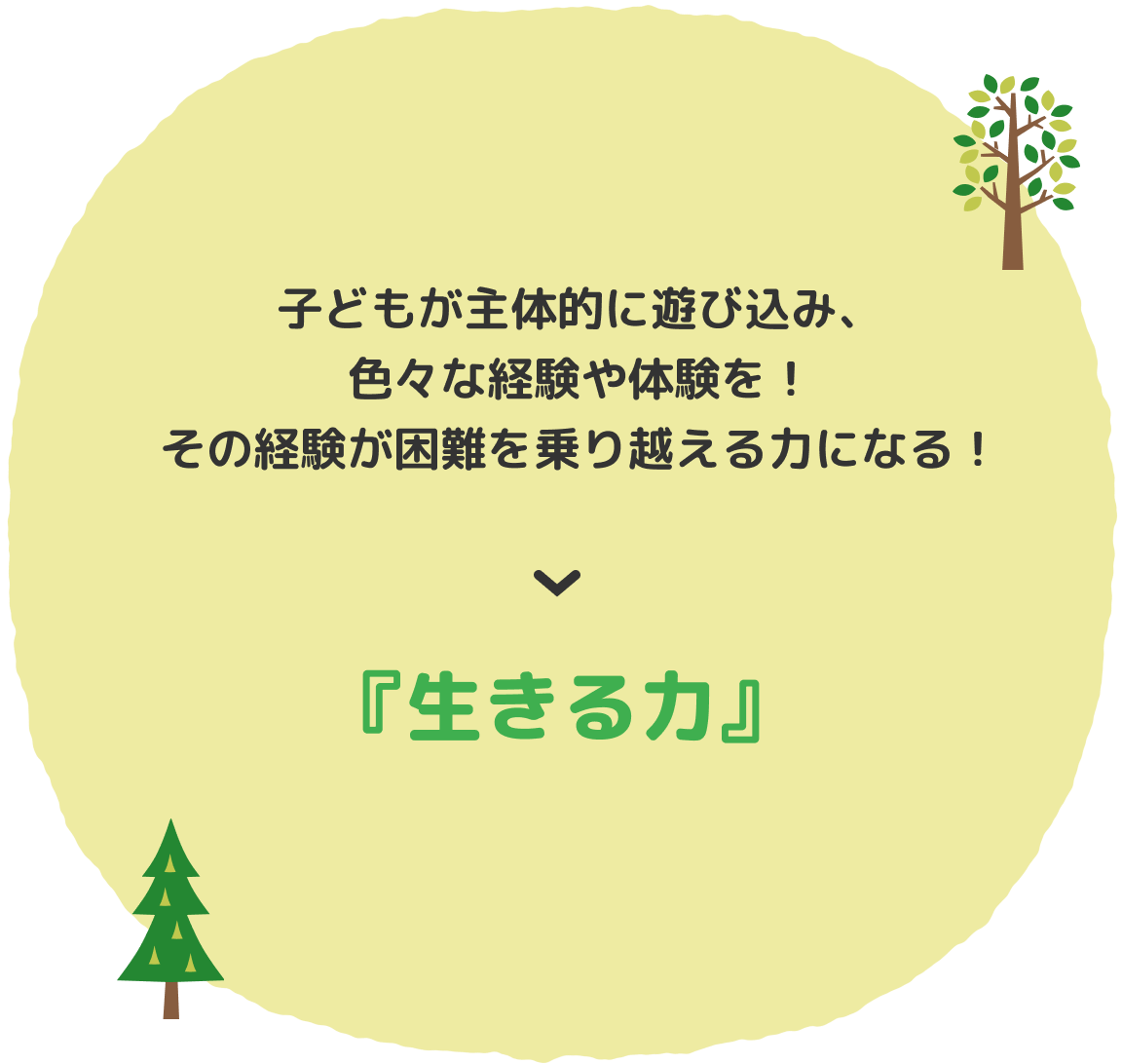
保育方針
(0・1・2歳児)
基本的な生活習慣を
身につけた子ども
心も身体も健やかに
よく遊ぶ子ども
教育方針
(3・4・5歳児)
興味のある遊びに
夢中になれる子ども
相手を思いやる
気持ちを持った
子ども
協調性があり
表現する力のある
子ども

園の想い

自然でも、屋内でも、あらゆる遊びの体験を通して、
思いやり、コミュニケーション能力、社会性、道徳性などを身につけていきます。
子ども達の意欲をかきたてるような魅力的な環境づくりを実践しています。
一人ひとりが、自分自身で考えて決断し、自発的に行っていくこと。
もっと楽しく遊ぶにはどうしたら良いか。
その工夫の繰り返しが子どもを成長させていきます。
子どもの主体性は、集団の中でも発揮されます。
自分の楽しみ以外にも、周囲の人との関りから、
相手の気持ちを考えることを覚え、思いやりが育っていくのです。
価値観の多様化する現代社会でも、しなやかにたくましく生きていけるような人間らしさを。
目に見えない力を育てる
非認知能力を育てる
想像カ・創意工夫する力・探求心や表現力・協調性・思いやり・意欲・積極性・乗り越える力・粘り強さなど、これら目に見えないけれど生きていく上で大切な力を「非認知能力」といいます。一方で「認知能力」と呼ばれるものは読み書き・計算・知識など数値化できる、主に小学校以降の学習を通して育つ力です。「非認知能力」が基盤となって、その上に「認知能力」が積み重なって育つので、乳幼児期には「非認知能力」を育てることが、非常に重要なのです。
乳幼児期は根っこを育てる
重要な時期
うちの子大丈夫?子育てはこれでいいの?と周りの子と比べてしまい不安になる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。それは子ども達の見える部分で比べているからでは?乳幼児期に大切なのは、意欲的に取り組んだり、相手を思いやったり、創意工夫といった「目に見えない力」を、じっくり時間をかけて養っていくことです。
五感を使った体験が
未来につながる
幼児期は知識を増やしたり正解を学んだりするよりも、実際に五感を使って体験し、感じることのできる環境と出会い、「どうなってるの?」「これなあに?」と興味関心を広げる時間と場所があれば、子ども達は自ら探究をはじめます。
だから
「遊び」
は大切
体験は遊びの中から生まれます。
子ども達が自ら遊び込める環境を大切にして「目に見えない力」を培っていきます。
幼児期の終わりまでに育ってほしい
10の姿
自然との関わり、
生命尊重
健康な心と体
自立心
社会生活との関わり
言葉による伝え合い
協同性
道徳性、
規範意識の芽生え
思考力の芽生え
豊かな感性と表現
数量や図形、
標識や文字等への
関心・感覚

園の特色
01 挑戦できる環境
子どもが主体的に遊ぶということは、遊び場の選択も主体的でなければなりません。遠軽町は、激しい寒暖の差がある地域です。その中でもこども園を通してたくましく戸外で遊ぶ子に育って欲しいと願っています。
戸外で季節を感じながら色々な気づきを通して成長して欲しいと思います。


02 目的を持った活動
遊びや生活の中で、自ら気付いたり、わかったり、できなかったことができるようになったり、豊かな体験をします。成長と共に気付きや出来るようになった経験を生かして、よりよい学校生活を営めるようサポートしていきます。
03 生きる力を培っていきます
「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を、遊びを通しての総合的な指導として保育していきます。

給食
子ども達の元気の源「食」
お米
お米は北海道産「ななつぽし」 を使用し、東神楽町のお米農家から直送のお米です。9・ 10月の収穫時期後からは、 新米です。子ども達に新米を届ける時は、お米そのものを味わってもらう為、 炊き立てのご飯をそのままで食べられるような献立に工夫しています。
アレルギー食も提供しています
ご家庭と相談してアレルゲンとなる食材を除く対応をしています。アレルギー食を用意する場合は、他の子どもと差が少なくなるように配慮しています。(栄養士と相談の上、対応しています)
週5日、自園調理の給食が
提供されます
献立は栄養士が作成し、子どもにとって必要な栄養バランスを考えた給食を提供しています。子ども達には継続して毎日食事が提供され、友達と一緒に準備や片付けをすることで、食事のマナーやルールが自然と身につきます。




